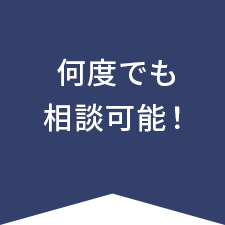2019年現在、大阪市内の地価(不動産)は上昇傾向ですが、中でもとくに好調なエリアはどこでしょうか?また上昇の反動でバブル崩壊のリスクはないのでしょうか?大阪府のデータより読み解きます。
不動産が過熱中といわれる大阪市内 中身は二極化の構図
ここでは、大阪市内の地価動向を区ごとに解説していきましょう。最近では、インバウンド(訪日外国人)の増加や2025年万博の開催により「大阪の不動産は熱い」という見方が強まっています。たとえば、2019年3月19日付の日経新聞の記事タイトルは「大阪・都心から湾岸へ 地価上昇、万博・IR期待先行」というものでした。
また同日の産経新聞は、「公示地価、大阪周辺にも波及 御堂筋線沿線が加熱」という見出しでした。こういったタイトルだけを見ると、大阪全体の地価(不動産)の勢いを感じます。しかし詳しいデータを読み込んでいくと、同じ大阪市内でも「絶好調エリア」と「停滞・不調エリア」の二極化が進んでいることが分かります。
そのため「資産価値を重視」して大阪に不動産を所有する場合は、好調エリアにセグメントすることがポイントです。
大阪市内の地価上昇エリアトップ5
大阪市内の好調エリアは具体的にどこなのかを確認していきましょう。大阪府が発行している「地価だより」によれば、2019年の公示地価をもとにした住宅地の変動率(前年価格に対する上昇率)のトップ5は次の通りです。
| 順位 | 区名 | 2019年度住宅地の変動率()内は前年度 |
|---|---|---|
| 1位 | 西区 | 9.5%(10.5%) |
| 2位 | 浪速区 | 8.2%(7.6%) |
| 3位 | 中央区 | 5.8%(3.6%) |
| 4位 | 北区 | 4.3%(4.5%) |
| 5位 | 福島区 | 4.2%(4.2%) |
これらの5区は、大阪市のほぼ中央部にあり、それぞれの区が隣接しています。総論でいえば、前年の2018年に変動率が高かった区は、引き続き2019年度も高い伸び率を維持していることが分かるでしょう。中央区を除けばおおむね前年と同じペースの上昇を示しています。ちなみに商業地のベスト5も順位は多少変わりますがこれらの5区です。
変動率1位・西区:おしゃれなエリアとモノづくりエリアの融合

ただ大阪・関西に在住の人以外はさきほどの変動率トップ5を見ても、どんなエリアが上位なのかイメージが沸きにくいかもしれません。トップの西区は駅名でいうと、九条駅(大阪メトロ中央線・阪神なんば線)をはじめ、阿波座駅、四ツ橋駅などが存在します。ランドマークでは、プロ野球チームのオリックス・バファローズの本拠地である京セラドーム大阪球場があります。
区の中央部を流れる木津川を境に、東西で違う表情を見せるのも特徴的です。東側は、オフィスや店舗が並ぶにぎやかな雰囲気で、とくに東南部の堀江エリアはおしゃれなショップが目立ち、若者の人気を集めます。これに対して西側は、製造・物流の会社が集中します。
変動率2位・浪速区、3位・中央区:訪日外国人が大挙する

変動率2位の浪速区は、人情豊かな大阪を象徴するシンボルタワー「通天閣」、その周辺には「ジャンジャン横町」がある新世界が広がります。他には、関空や伊丹空港行きのバースターミナルと商業施設をミックスした「OCAT」、南海電鉄なんば駅直結の「なんばパークス」をはじめ現代的な施設も盛りだくさんです。
変動率3位の中央区は大阪城のある場所。浪速区と並んで訪日外国人が大挙しているエリアです。大阪難波駅、心斎橋といった活気のあふれる街の駅も中央区内にあります。
大阪の不動産はバブルといえる状態にあるのか?
大阪の地価変動率が好調だと、高止まりや反動による下落を心配する向きもあるかもしれません。この点については、大阪府が示している「地価動向指数」が参考になりそうです。過去の地価動向と現在の地価を客観的に比較できます。この指数は、1983年1月の大阪府の公示地価を100として、それと比べてある時点の公示地価がどれくらいかを現したものです。
1989~1991年ごろのバブル期は300以上でバブル崩壊とともに指数は大きく下落。2019年の段階ではやや盛り返して88.7になっています。つまり、いくら大阪の不動産が好調だといってもバブル期には到底及ばないのです。今後、市中心部の地価上昇が大阪市全体、大阪府全体に波及していくかが注目されます。
人気の記事ランキング
キーワードから記事を探す
注目の不動産投資セミナー
大阪・京都・神戸

大阪・京都・神戸の物件を希望の日程で見学できる物件見学会を開催中!
- 日程
- 適時開催
- 会場
- 見学対象の区分中古マンション
名古屋

名古屋の物件を希望の日程で見学できる物件見学会を開催中!
- 日程
- 適時開催
- 会場
- 見学対象の区分中古マンション