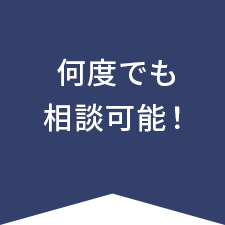日本銀行(日銀)が掲げる、年2%の物価上昇率。普段は意識しませんが、この物価上昇が続けば、私たちの生活に大きな影響を与えます。生活を苦しくするリスクのあるインフレを、プラスの力に変えるための対策をご提案します。
政府がインフレにこだわる理由 インフレが続くと国の借金が減る?
長らく日本はデフレ状況にあり、デフレ脱却こそが日本経済に不可欠とされてきました。アベノミクスが掲げた「三本の矢」のうち、第一の矢として放たれたのが「大胆な金融政策」です。日銀はこれまでにない金融緩和を行うことで、市場に出回るお金の量を増やし、年2%の物価上昇を目標として掲げてきました。
まだ目標達成には至っていませんが、物価は着実に上昇しており、日銀の黒田東彦総裁は金融緩和策を継続することを決めています。政府がインフレ政策にこだわる理由は、物価上昇による企業の売り上げ増、従業員の賃金アップ、購買意欲の向上などで、経済を活性化させる狙いがあるとされています。
一方で、一部の専門家の間では、次のような指摘もあります。インフレは相対的に貨幣の価値を下げるため、日本国債の価値も実質的に目減りし、一気に借金を圧縮できる……。確かに毎年2%の物価上昇が続くと、およそ35年後には借金の実質価値が半減している計算になります。
国の借金が減るのは歓迎すべきことですが、一方で国民の生活はインフレで苦しくなることが予想されています。
貯金・保険・年金はインフレに弱い

もしインフレが続くとすると、市場に出回るお金の総量が増えた分、その価値が逆に下がっていくことになります。
例えば、今まで100円で買うことができていた商品の価値は、インフレ率200%になると、2倍の200円になってしまうことを意味しています。2%の物価上昇が安定して10年間続いた場合、現在1万円の物は1万2,190円に、30年後には1万8,114円の価値になるという試算になります。年率2%という数値はとても小さく感じますが、長期的には無視できない数字なのです。
もちろん、物価が上がれば企業が儲かるので、従業員の賃金も当然ながらアップするでしょう。しかし問題は、預金と保険です。なぜなら、将来必要となるお金を現在の貨幣価値で準備することになるからです。
また、退職後の強い味方であるはずの老齢年金も、現在はマクロ経済スライドを採用しています。物価だけではなく、さまざまな社会的要因によって変動させるため、公的年金の支給額は物価の上昇率よりも小さな上がり幅となる可能性が高いのです。
今後も、物価上昇が考えられる状況においては、インフレに対応できる資産運用が必要でしょう。
インフレをプラスの力にするための3つの対策

インフレ対策1 現金主義から資産運用にシフトする
現金の実質価値が目減りしてしまうのですから、銀行預金やタンス貯金などに頼らず、資産運用を意識するべきです。物価上昇率を上回る利回りが理想ですが、たとえ利率が低めであっても、現金をそのまま寝かせておくよりも資産を増やせる可能性があります。
例えば、投資に詳しい方であれば、自身で株式投資などをしてもいいかもしれません。投資が全く分からないという方であれば、投資信託でプロにお任せする方法もあります。ただし、大きな利益にはそれ相応のリスクがあるので、分散投資や長期保有などでリスクを軽減することも重要です。
インフレ対策2 金や不動産などを持つ
現金ではなく、金に代表される貴金属、不動産で資産を守る方法もあります。金地金や土地などの現物資産は、インフレ時には相応の値上がりが見込まれます。ただし、管理料や手数料といった経費がかかるということも考慮する必要があります。
インフレ対策3 あえて借金をして投資に回す
金融緩和によって、日本の金利が超低水準にある今、これを好機と捉える富裕層もいます。あえて借金をして手元のキャッシュを多くすることで、事業を回し、運用利益を大きくするのです。利息が少ないばかりか、インフレが進むことによって借金が実質目減りしていくことにもなります。
また、お金を借りて不動産投資をする人もいます。人口減が続く日本ですが、世帯数は逆に増加しており、まだまだ不動産投資にも可能性はあります。
とはいえ、借金にはリスクがあるため、運用利益と返済コストとのバランスを考えて計画的に借り入れをするべきでしょう。
人気の記事ランキング
キーワードから記事を探す
注目の不動産投資セミナー
大阪・京都・神戸

大阪・京都・神戸の物件を希望の日程で見学できる物件見学会を開催中!
- 日程
- 適時開催
- 会場
- 見学対象の区分中古マンション
名古屋

名古屋の物件を希望の日程で見学できる物件見学会を開催中!
- 日程
- 適時開催
- 会場
- 見学対象の区分中古マンション