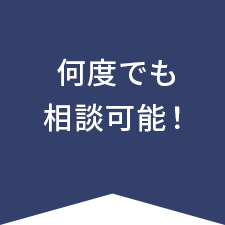「老後2,000万円問題」をきっかけに、資産形成を始めた方々も多いでしょう。そこで資産の運用や投資を本格化させる前に、ぜひ知っておいていただきたいのが「資産三分法」。この知識を持っているか否かで、資産の安定性も変わってくるかもしれません。本記事では、資産三分方のポイントを解説します。
資産三分法のメリット「安定感のある資産形成がしやすくなる」

資産三分法とは、資産を「現金」「土地(不動産)」「株」の3つに分けて所有するポートフォリオ理論です。このうち、現金には預金や金などの資産、株には債券や投資信託などを含めて考えるとよいでしょう。
資産三分法を採用するメリットは、値動きの違う幾つかの資産を組み合わせることで、ボラティリティー(価格変動)を緩和できることにあります。これにより、安定性のある資産形成がしやすくなるといわれています。
資産三分法を選択すると、好景気の局面では、それぞれの資産の値上がりを享受することができます。例えば、不動産の値上がりが著しい一方で、株は緩やかな値上がりといったバラつきがある場合でも、リターンがならされます。逆に、不景気の局面では、価値の下落を緩和する効果があります。例えば株価が暴落しても、その影響が不動産に本格的に波及するまでにはタイムラグが発生します。
ポートフォリオに柔軟性を持たせることも大切

ポートフォリオの比率には、いろいろな考え方があります。現金・不動産・株の3カテゴリの資産価値が等分になるようにポートフォリオを組む。あるいは、高リターンを狙って株の比率を高める。
ここで大切なことは、どのような比率でポートフォリオを組むにしても、柔軟性を持たせることです。ずっと同じ比率で資産を保有するのではなく、国内外の景気動向やインフレ・デフレの大きな流れを見ながら比率を調整していくことで、リターンを享受しやすく、ダメージを吸収しやすい資産管理が可能になります。
一例を挙げると、中長期的に業績が伸び悩む企業が多いと見るなら株の比率を下げ、金や不動産などの現物資産や預金の額を増やすといった具合です。
資産三分法は実行するのが大変 専門家の力を借りて効率化

ここまで見てきたように、資産三分法の考え方自体はとてもシンプルです。その一方で、資産三分法をいざ実行しようとしても、手間がかかってしまうのが現実です。
例えば、株といっても国内株や海外株などがありますし、国内でも代表銘柄・ベンチャー銘柄などに分けられます。また大型優良銘柄・成長型・割安優良型というように、値動きのタイプによっても細かく分類されています。
あるいは不動産で考えても、一棟物件・区分マンション・商業ビルなどがあり、それぞれに立地や築年数などを考えると、選択肢の幅は限りなく広がります。また金で考えてみても、金貨・金地金・金ETF(上場投資信託)などの形態があります。
この選択肢の中から的確な判断をしていくためには、各カテゴリの勉強が必須で、実行までにかなりの時間がかかることが想定されます。またいくら勉強しても、自分だけで選択するには知識が追いつかないことも考えられます。
そのため、各カテゴリの専門家の力を借りながら、ポートフォリオを組んでいくことも必要になるでしょう。例えば、株をメインにした投資信託を選ぶ際には、ファンドマネージャーという専門家の力を借りることができます。
また不動産であれば、あるカテゴリに特化した会社をパートナーにすることで、投資家自身は基礎知識を押さえる程度でも、資産をスムーズに運用することが可能です。例えば、一棟物件に強い、区分マンションに強い、特定エリアに特化しているなど、不動産会社にはそれぞれの専門分野があります。
一時的な儲けや損失に迷わされずに分散投資を
資産三分法を行う上で、注意しなければいけないこともあります。それは、分散投資の重要性を頭で分かっていても、儲かったカテゴリに偏ったり、逆に損失の発生したカテゴリを避けたりしがちになるということです。安定的に資産形成をしていくためには、一時的な儲けや損失に迷わされず、分散投資の大切さを常に意識することが求められます。
人気の記事ランキング
キーワードから記事を探す
注目の不動産投資セミナー
大阪・京都・神戸

大阪・京都・神戸の物件を希望の日程で見学できる物件見学会を開催中!
- 日程
- 適時開催
- 会場
- 見学対象の区分中古マンション
名古屋

名古屋の物件を希望の日程で見学できる物件見学会を開催中!
- 日程
- 適時開催
- 会場
- 見学対象の区分中古マンション