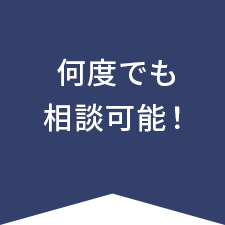日本では、憲法第25条に定められている「健康で文化的な最低限度の生活」を背景に、社会保障制度が整備されています。大きく分けると「社会保険」「社会福祉」「公的扶助」「保険医療・公衆衛生」という4つの概念によって成り立っています。これらを“もしものときの備え”として考えると、受けられるサービスとしては非常に幅広く、かつ手厚いのが特徴です。
一方で、こうした社会保障制度について熟知している人はそれほど多くありません。また民間の保険や保証サービスに関心をもっている人はたくさんいるものの、公的なサービスとの兼ね合いを考えておらず、必ずしも効率的に利用できているとは言えないのが実情です。そこで本稿では、押さえておくべき社会保障制度の中身について見ていきましょう。
資産形成は「社会保障制度」を軸に考える

そもそも、なぜ社会保障制度というものが用意されているのでしょうか。社会保障は、個人の責任や個人の努力だけでは対応できないリスクに対し、相互支援の仕組みを提供しています。加えて、そのような相互の連携でも困窮してしまう場合には、必要な生活保障を行うことで、国民の生活を支えているのです。まさに社会のセーフティネットです。
しかもこれらの社会保障は、生涯にわたって提供されることを前提としています。人生は、いつ何が起こるか分かりません。中には予測できるような事柄もありますが、必ずしも回避できるとは限らず、時に人生を大きく左右する可能性もあります。それは資産形成に関しても同様です。何が起こるのか分からないからこそ、社会保障について理解しておくことが大事といえます。
社会保障制度の概要
資産形成には、「攻めの資産形成」と「守りの資産形成」があります。攻めの資産形成とは、自らの資産を積極的に増やしていくことです。守りの資産形成とは、自らの資産を維持することに力点が置かれています。このうち社会保障制度についての理解を深めることは、守りの資産形成をより効率的なものにするのに役立ちます。以下、制度の概要をチェックしていきましょう。
社会保険
社会保障制度における「社会保険」とは、事故や病気など人々の生活困難をもたらす事象に対処するために、生活の安定を図ることを目的とした制度のことです。その対象は、出産や死亡、老齢、生涯、失業などと幅広く、また保険への加入は強制となります。私たちは、毎月行っている社会保険料の支払いを通じて、もしもの場合に備えているわけです。
社会福祉・公的扶助
一方で「社会福祉」とは、障害者や母子家庭など何らかのハンディキャップを負っている人を対象とした支援制度です。児童福祉や障害者福祉などがあります。社会福祉に似ている概念として「公的扶助」がありますが、こちらは生活に困窮する人々が対象です。生活困窮者に対して生活保護を提供し、最低限度の生活を保障しつつ、自立を促します。
保険医療・公衆衛生
社会保障制度における「保険医療・公衆衛生」とは、人々が健康に生活するために行う予防や衛生のための制度です。具体的には、以下のようなものがあります。
・医療従事者や病院などが提供する医療サービス
・疾病予防および健康づくりなどの保健事業
・母性の健康と児童の出生および育成を増進する母子保健
・食品や衣料品の安全性を確保する公衆衛生など
セーフティネットを軸にした資産形成を
このように社会保障制度というのは、もしものときの備えとして、さまざまな側面から機能しています。資産形成という側面から考えると最低限の備えをしつつ、必要な場面では社会保障制度の活用を視野に入れておけば、より効率的な運用も可能です。まずは「どのようなシーンでどのような制度が使えるのか」を知り、資産形成の検討に役立てていきましょう。
人気の記事ランキング
キーワードから記事を探す
注目の不動産投資セミナー
大阪・京都・神戸

大阪・京都・神戸の物件を希望の日程で見学できる物件見学会を開催中!
- 日程
- 適時開催
- 会場
- 見学対象の区分中古マンション
名古屋

名古屋の物件を希望の日程で見学できる物件見学会を開催中!
- 日程
- 適時開催
- 会場
- 見学対象の区分中古マンション