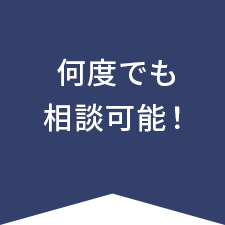家賃維持や入居者確保の面でリスクが低い大都市新築ワンルームですが、中古物件に比べると投資金額が多くなってしまうので、最終的な出口戦略として『売却』も念頭に置く必要があります。
難しいのは「いつ売るか」です。本記事では具体的な事例を検証しつつ、売却時期について考察します。
賃貸物件のリセール価格は収益還元法によって決まる
不動産取引価格の評価は、①原価法・②取引事例比較法・③収益還元法のうちいずれかの方法が用いられます。
①原価法=不動産の再調達原価に着目して価格を求める方法
②取引事例比較法=類似の不動産の取引事例価格に着目して価格を求める方法
③収益還元法=不動産が将来生み出す収益に着目して価格を求める方法
分譲マンションや土地の場合は、②取引事例比較法が用いられることが多いようです。取引事例比較法では、市場において発生した取引事例を価格判定の基礎とするため、多数の取引事例が存在するエリアでなければ、業者によって不動産の評価がバラバラということになりかねません。
一方で賃貸物件の場合、その取引価格は③収益還元法によって評価されることが多いようです。収益還元法は、(a)直接還元法と、(b)DCF(ディスカウントキャッシュフロー)法という2つの方式があります。いずれも不動産の収益価格を割り出す際に、家賃収入など一定期間の「純収益」と、「還元利回り」という概念を用いているのが特徴です。
(a)直接還元法
直接還元法では、次の算式で取引価格を算定します。簡便なのが直接還元法の利点と言われています。
(算式)(国土交通省HPから引用)
求める不動産の収益価格(※1)=一期間の純収益(※2)÷還元利回り(※3)
※1 端的に言えば、対象不動産の試算価格のことを指します。
※2 家賃収入などの総額から諸経費を差し引いた残りの金額を指します。
※3 端的に言えば、不動産の収益性を示す指標のことを指します。資産の種類や条件によって異なりますが、おおむね一般的住宅では5~7%、事業用は8~10%が目安です。
直接還元法の場合、単純に言えば、一期間の純収益の値が同じならば、還元利回りが下がるほど不動産の収益価格が上がる、求める不動産の収益価格が上がるほど還元利回りは下がるということになります。
(b)DCF法
一方で経年による収益低下を織り込んで算定されるのがDCF法です。ご参考までに以下に算式を挙げますが、かなり複雑なものになっています。
(算式)(国土交通省HPから引用)

直接還元法とDCF法のどちらを適用するかについては、ケースバイケースです。例えば、収益の見通し等について詳細に計算する際は原則としてDCF法を適用し、併せて直接還元法を補充的に適用することでDCF法の計算結果を検証することになります。
金利と利回りは連動する

不動産の収益性を示す有名な指標の一つに「期待利回り」という指標があります。簡単に言うと、投資額に対してどれくらいリターンが見込めるかを示す期待値のことを指します。
「還元利回り」と「期待利回り」は、厳密には異なる概念ですが、「期待利回り」は収益還元法における「還元利回り」を求める方法に準じて求められます。したがって、「期待利回り」は「還元利回り」に準じて考えることができます。
前掲した直接還元法の計算式から分かる通り、収益還元法のうち特に直接還元法で賃貸物件の取引価格を算定する場合、「期待利回り」が下がるほど不動産の価格が上がると考えることができます。また、一期間の純収益の値が同じならば、不動産の収益価格が上がるほど期待利回りは下がると考えることもできます。
(前掲)直接還元法算式
求める不動産の収益価格=一期間の純収益÷還元利回り
ここ10年でワンルームマンションの期待利回りは大都市圏を中心に大きく低下しています。例えば東京城南地区では、ここ10年で期待利回りが6.0%から4.5%まで大きく低下しました。
この原因はいろいろ考えられますが、日銀の金融緩和政策による金利低下の影響で、物件価格が高騰した影響が最も大きいと推察されます。金利低下は世界的なトレンドであり、日本でも長期プライムレートが2010年の1.65%から2017年には1.00%にまで大きく低下しました。
つまり、金利が下がる→不動産の価格高騰→期待利回り低下という連鎖が起こっていると推察されます。
上記の通り、収益還元法のうち特に直接還元法で賃貸物件の取引価格を算定する場合、期待利回りが低いほど不動産の価格が高いと考えることができます。したがって、シンプルに考えるならば、ワンルームマンションを高く売りたいなら、金利が低下している時期を選ぶべきなのです。
経年による家賃低下から売り時を考える
売却時期では、経年による家賃低下も考慮しなければいけません。総務省統計局が発表した調査結果によると、家賃収入は1年間で約0.8%低下するとされています。そうすると端的に言って、10年で約8%、20年で約16%も家賃収入が低下することになります。そして家賃収入低下は、ダイレクトに取引価格に影響します。
経年による集客力低下も、大きな問題です。一般的に、築年数20年を超えると家賃相場も大幅に下がります。買主の立場に立ってみると、築10年の物件なら残り10年は安定した家賃収入を見込むことができますが、築15年だと築20年まであと5年しかありません。
上記総務省統計局が発表した調査結果によると、不動産の価格を示す指標である住宅資産額はなんと10年で約20%、20年で30%以上も下落するとされています。これは家賃収入の低下を上回る下落率です。
大都市新築ワンルームは収益面で魅力の高い投資商品であり、その点はリセール市場における価格競争力の強さに現れます。こうした強みを活かすためにも金利推移・経年劣化などに目配りし、有利な売却時期を見極めることが大切なのです。
人気の記事ランキング
キーワードから記事を探す
注目の不動産投資セミナー
大阪・京都・神戸

大阪・京都・神戸の物件を希望の日程で見学できる物件見学会を開催中!
- 日程
- 適時開催
- 会場
- 見学対象の区分中古マンション
名古屋

名古屋の物件を希望の日程で見学できる物件見学会を開催中!
- 日程
- 適時開催
- 会場
- 見学対象の区分中古マンション