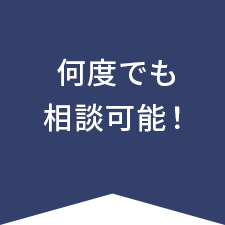2019年5月、いよいよ平成が終わりを告げ、新元号を迎えます。改元を間近に控え、テレビや雑誌などでも平成の30年間を振り返る特集を見かけるようになってきました。
平成の前半20年は「失われた20年」と言われるほど経済的に低調な時代で、その後は好景気と不景気を繰り返したり、経済データは好調であっても一般市民は好景気を実感できなかったりなど、昭和の高度経済成長やバブル経済の幻影を引きずりながら、浮き沈みのある経済が続いていました。
ここでは、平成30年の歩みの中で特に注目度の高かった7つの経済ニュースを、話題の大きさ順に振り返ります。
1.平成2年(1990年) 不動産融資の総量規制
バブル経済の崩壊を直接招いたとして知られている大蔵省(現・財務省)の通達です。
平成元年(1989年)12月29日、日経平均株価は過去最高の3万8,915円を記録。加熱するバブル景気は土地の値上がりを背景とした過剰な不動産投資を主要因として始まりました。そこで、大蔵省は金融機関の融資を抑制。その結果、不動産への投機が伸び悩み、景気循環による低迷なども合わさり、バブル崩壊を迎えます。
2.平成元年(1989年) 消費税導入
今年10月から10%への増税で話題となっている「消費税」が導入されたのも平成です。竹下登内閣で消費税法が施行され、税率3%からスタート。その後、平成9年(1997年)に5%、平成26年(2014年)に8%と税率が上がり、今年2019年10月には10%への引き上げが決まっています。消費税に関しては現在もなお「低所得層ほど税負担が大きい」「使いみちを社会保障費に限定するべき」などさまざまな議論が続いています。
3.平成20年(2008年) リーマン・ショック

アメリカのサブプライムローンと呼ばれる住宅ローンの不良債権化が深刻となり、投資銀行の大手だったリーマン・ブラザースが倒産しました。当時、アメリカは証券バブル状態だったため、その影響がアメリカ国内外に広がり、日本は円高による不景気に陥ります。
翌年の平成21年(2009年)には、日経平均株価が7,054円にまで下落しました。これはバブル崩壊後の最安値です。
4.平成9年(1997年) 山一證券自主廃業
バブル崩壊から続く長い金融不況の中、四大証券会社の一つ、山一証券による約2,600億円の債務隠しが表面化します。社長が号泣しながら老舗証券会社の自主廃業を発表する会見は、世間に衝撃を与えました。この年は、都市銀行であった北海道拓殖銀行の破綻も起こるなど、企業の経営破綻が相次ぎ、大手企業の権威や終身雇用制など、戦後日本を支えた国民の意識が変化したきっかけともいえます。
5.平成30年(2018年) 日経平均株価の乱高下が続く
10月2日の終値2万4,270円は約27年ぶりの高値として大きな話題となりました。その一方、世界同時株安や米中貿易摩擦など、世界経済のあおりを大きく受け、12月28日の終値は2万14円となり、7年ぶりに年間12%安で終了しました。国内株式の乱高下の原因は、海外投資家の売り越しが約13兆円もの巨大な規模に膨らみ、日銀の金融政策も思うように効果を出せていないためといわれています。
6.平成19年(2007年) トヨタ自動車の営業利益が国内初の2兆円突破
この年、トヨタ自動車は日本企業初となる営業利益2兆円を達成しました。営業利益だけでなく純利益も過去最高益となった背景には、円安傾向が続いたことや、販売台数が世界的に好調な推移を見せたことなどがあります。海外の製造業が見習うトヨタ方式「カイゼン」をはじめ、国内のみならず世界的に経済をリードするトヨタの存在感は、平成の後もますます強まりそうです。
7.平成18年(2006年) ライブドア事件
ライブドア堀江貴文元社長が、ライブドアグループの買収に関連して旧証券取引法違反で逮捕。堀江元社長は懲役2年6ヵ月の実刑判決を受け服役しました。
ライブドアの社長就任以来、2004年のプロ野球への参入表明、2005年のニッポン放送株大量取得など、日本社会を揺り動かす経営的手腕で時代の寵児となりました。
激動の経済が続いた平成の後はどうなる?
バブル経済から低成長時代へと社会が大きく移り変わった平成の日本。多様な経済ニュースに彩られた30年でした。新元号となる次の時代は、好景気を期待したいものです。
人気の記事ランキング
キーワードから記事を探す
注目の不動産投資セミナー
大阪・京都・神戸

大阪・京都・神戸の物件を希望の日程で見学できる物件見学会を開催中!
- 日程
- 適時開催
- 会場
- 見学対象の区分中古マンション
名古屋

名古屋の物件を希望の日程で見学できる物件見学会を開催中!
- 日程
- 適時開催
- 会場
- 見学対象の区分中古マンション