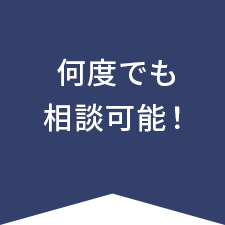国内株式の値動きへの影響力が大きいといわれるGPIF。投資家の間ではGPIFのポートフォリオをマークすべきといった声も聞かれます。GPIFはそもそもどんな考え方で運用を行っているのでしょうか。また運用成績は?気になるGPIFの中身を解説します。
GPIFが長期運用を重視する理由-過去のデータから安定運用

GPIFとは年金積立金管理運用独立行政法人のことで、厚生労働大臣から委託を受けて年金積立金の運用・管理をしている組織です。GPIFでは長期運用を主に行っています。株式や債券の短期の運用はプラスやマイナスに大きく振れる可能性も少なくありません。グローバル視点の長期運用は安定的に収益を得られる傾向にあるため、年金の運用には合っているのです。
GPIFでは、この長期運用の信頼性を下記のように公式サイトで解説しています。仮に1969年に「国内債券」「国内株式」「外国債券」「外国株式」をそれぞれ100万円分ずつ購入し、約50年後の2018年にいくらになったかを試算すると、一番収益が少ない「外国債券」でも515万円になり、約5倍に増えているそうです。
また最も収益が多かった「外国株式」で2,806万円と28倍に増えているとのこと。このように長期投資は大きな収益を出していることがわかります。
参照:GPIF「長期的な観点からの運用」
運用開始から2018年までの運用成績はプラス65兆円超
GPIFが今のような長期運用をはじめたのは2001年度からです。運用開始から2018年までの運用実績は、プラス 3.03%(プラス65.8兆円)で順調に運用が行われていることがわかります。 ちなみに最近のGPIFは安倍晋三政権の運用改革のもと株式市場に突然表れ、幅広い銘柄を一気に買いあさることから市場関係者の間では「クジラ」と呼ばれるようになりました。
長期的に安全で効率的な運用を行うには、基本になる資産構成割合(ポートフォリオ)を決めて運用することが大切だと考えられています。GPIFでは経済環境や市場環境に対応しながら成果を出すために、ポートフォリオの見直しをしてきました。2019年現在は2014年10月に定められたポートフォリオに基づき運用しています。
現状のポートフォリオ内訳は「国内債券」35%、「国内株式」25%、「外国債券」15%、「外国株式」25%です。ただし乖離許容幅があるので、市場動向に合わせてその都度比率は調整されています。2014年の変更では、それまで60%を越えていた「国内債券」の割合を35%まで減らし、他の3種の割合を高めました。特に国内、外国の株式が割合を高めていて、2つを足すと50%を超える割合となっています。
直近でも成果を出しているが「リスクが高まっている」との声も

長期運用では成果を出しているGPIF ですが、最近の運用成績はどうなっているのでしょうか。2018年度単年で見ても、プラス 1.52%(プラス2兆3,795億円)で長期に比べれば割合は低いものの、後半は世界経済が不安定だった中、健闘した結果といえます。長期でも短期でもそれなりの成果を出しているGPIF。
しかし2019年4月には、会計検査院が「株式比率が50%というポートフォリオはリスクが高まっている」として国民に丁寧な説明を行うよう警鐘を鳴らしています。これは2018年度第3四半期だけを見た場合、期間収益額でマイナス14兆8,038億円と大きなマイナス運用になった影響です。
ESGカテゴリへの投資を重視する方向に舵を切ったGPIF
最近のGPIFが新しい手法として取り入れようとしているのがESGといわれるカテゴリです。ESGは環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の頭文字を合わせた言葉です。投資先を測る指標として、一般的に企業のキャッシュフローや財務情報が使われます。しかしESGはそれに加え、温暖化対策をしているかといったこと(環境)や、女性社員が活躍しているか(社会)といった、非財務情報も投資判断の材料にするといった考えです。
ESG投資はリスク調整後のリターンを改善する効果があるといわれています。GPIFは「ESG活動報告」を2018年から発行していますが、ESGの効果が表れるまでには長い時間がかかるといわれていますので、長期的に見ていく姿勢が必要です。巨大クジラは、新しい旅路を見つけて泳ぎ始めたといえるでしょう。
人気の記事ランキング
キーワードから記事を探す
注目の不動産投資セミナー
大阪・京都・神戸

大阪・京都・神戸の物件を希望の日程で見学できる物件見学会を開催中!
- 日程
- 適時開催
- 会場
- 見学対象の区分中古マンション
名古屋

名古屋の物件を希望の日程で見学できる物件見学会を開催中!
- 日程
- 適時開催
- 会場
- 見学対象の区分中古マンション