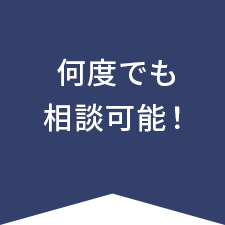少子高齢化に伴う日本経済の持続的低迷が危惧されている中、財政健全化という観点から、膨らみ続ける“国の借金”の問題を解決しなければなりません。2019年7月に行われた参議院選挙においても、安倍晋三首相が率いる自民党は「プライマリーバランス(基礎的財政収支)の健全化」などの公約を掲げて国民に訴えたほか、10月からは消費税10%への増税を予定しています。
一方で、別のムーブメントも起きています。それは、「現代貨幣理論(MMT)」を巡る議論です。先の参院選では、山本太郎氏が代表を務める「れいわ新選組」がMMTの有効性を訴え、結果的に220万票以上を獲得しました。他にも要因があることを考慮に入れても、その影響力は大きかったと考えられます。では、MMTとはいったいどのような経済理論なのでしょうか。
現代貨幣理論(MMT)とは

アメリカで史上最年少の下院議員となったアレクサンドリア・オカシオ=コルテス氏をはじめ、数々の著名人が言及して議論の的となっている「現代貨幣理論(MMT)」。その内容は、端的に言うと「自国通貨を持つ国は財政赤字を心配することなく、むしろ積極的に財政支出を拡大するべき」という経済理論です。
もちろん、ただ支出を増やせばよいというわけではありません。あくまで、懸念されるインフレの度合い(ハイパーインフレーションなど)に近づかないレベルを考慮しつつ、財政出動を行うべきだという発想が根底にあります。もし過度なインフレが起こりそうであれば、増税や政府支出の削減といった緊縮的な政策に転じることで、状況の悪化は避けられるというのです。
MMTの特徴とその背景
MMTに対し、経済学者のポール・クルーグマン教授や、米国連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長、投資家のウォーレン・バフェット氏などは批判的な立場を取っています。また日本においても、MMTの提唱者であるステファニー・ケルトン教授が来日するなどの動きはあるものの、慎重論が根強く残っています。今後の動向も含めて、MMTの中身について探っていきましょう。
MMTが機能する仕組み
そもそもMMTとは「Modern Monetary Theory」の略称で、日本語では「現代貨幣理論」や「現代金融理論」などと訳されています。その理論は、「自国通貨を自国の中央銀行が発行している国であれば、どれだけ財政赤字が膨らんでも、新たにお金を発行して支払うことができる」というものです。つまり、国の借金が「自国通貨建ての債務」であることが前提として挙げられています。
なぜMMTが脚光を浴びているのか
MMTの原型は20世紀初頭にまでさかのぼり、1990年代に成立したといわれ、それほど新しい経済理論ではありません。では、なぜ今日の日本でも注目されているのでしょうか。一つには、やはりアベノミクスが思ったほどの成果を上げられていないためだと考えられます。確かに、大手企業の業績や雇用状況は回復しつつあるものの、いまだ目標の物価上昇率2%にまで達する見通しはたっていません。
MMTの不安因子
経済政策を最優先にしてきた安倍政権において、「抜本的な景気回復が実現できていない」という実感が日本社会にまん延し、その反動でMMTに注目が集まる要因となっているようです。ただ、ハイパーインフレーションへの懸念や、インフレを操作できるかどうかが疑問視されていることなど、MMTにも不安因子が付いて回ることは否めません。特に日本では、財政法第5条で中央銀行が国債を直接購入できないと定められており、実現の可能性には疑問符も付いています。
議論の中身を知っておくことが大事

最後に、MMTを巡る議論でよく言及されている「信用創造」にも触れておきましょう。経済の構造は、一般的に「人々が銀行に預けたお金で、銀行が企業に貸し出すことにより、経済が循環する」と認識されています。しかし信用創造という概念では、「銀行が企業にお金を貸し出すことで預金(残高)が生まれ、経済が循環していく」という風に考えます。その概念を当てはめると、政府の支出(赤字)が拡大すれば、経済循環を創出できるということになりますが、その是非を決めるのは、私たち国民の判断にかかっています。
人気の記事ランキング
キーワードから記事を探す
注目の不動産投資セミナー
大阪・京都・神戸

大阪・京都・神戸の物件を希望の日程で見学できる物件見学会を開催中!
- 日程
- 適時開催
- 会場
- 見学対象の区分中古マンション
名古屋

名古屋の物件を希望の日程で見学できる物件見学会を開催中!
- 日程
- 適時開催
- 会場
- 見学対象の区分中古マンション