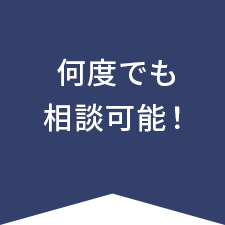2019年の時点では、地価は都心部で堅調な推移を示していますが、ほとんどの地方では相変わらず地価下落が続いています。その原因は、少子高齢化や大都市への流出に伴う人口減少が最も大きいとされています。
今、地方を苦しめている少子高齢化と人口減少は、首都圏でもすでに進行しており、日本中が直面している問題です。そしてこの問題は、地価動向にも直接影響を与えます。今後の不動産市場は果たしてどうなっていくのか、また活路を見いだすために不動産投資戦略はどうあるべきかについて考えてみましょう。
格差が拡がる不動産市場

2019年9月に国土交通省が公表した地価調査によると、全用途平均の全国の基準地価は+0.4%と、2年連続で上昇しました。ただし、地価上昇はあくまでまだら模様です。3大都市圏(首都圏・中京圏・近畿圏)が+2.1%、中核4市(札幌市・仙台市・広島市・福岡市)が+6.8%と上昇基調を強める一方で、地方圏は持ち直しの傾向が見られるものの、△0.3%と相変わらずマイナス圏に沈んでいます。
近畿圏でも、大阪府・京都府以外の各県(奈良県・兵庫県・和歌山県・滋賀県)の住宅地は相変わらずマイナスです。府県内でも、格差が広がっています。例えば住宅地では、大阪府全体は0.4%伸びていますが、大阪市内(+1.0%)・北部(豊中市・池田市・茨木市等+0.8%)・堺市(+1.6%)が好調な一方で、東部(柏原市・東大阪市・八尾市等△0.2%)・南河内(藤井寺市・富田林市・河内長野市等△0.6%)はマイナスから脱していません。
また大阪市内の住宅地は、今年は全ての区で横ばいまたはプラスとなりましたが、人気エリアの天王寺区(+4.8%)・浪速区(+4.3%)・福島区(+4.6%)と、東成区(0.0%)・生野区(+0.4%)・東住吉区(+0.2%)といったエリアとの差が開いています。
減り続ける日本の人口

人口統計によると、日本の人口は2008年の1.28億人をピークに減少へ転じました。2030年までで人口が増えるのは東京都と沖縄県だけで、2030年以降は47都道府県の全てにおいて人口が減少するとされています。
2030年の総人口は、2015年を100とすると、2030年には93.7にまで低下します。3大都市圏や中核4市(札幌市・福岡市・広島市・仙台市)がそれほど落ち込まない一方、地方は厳しい状況にさらされており、高知県・青森県は85以下、秋田県に至っては80を切ると推計されています。
なにわの地価動向を左右する人口予測と二極化
では、大阪の地価は今後どう動いていくのでしょうか。決め手となるのは、やはり人口推移です。
将来人口推計によると、2030年の大阪府の人口は、2015年を100とすると93.5にまで落ち込みます。その一方で、近畿圏のみならず西日本における経済・交通の要所でもある大阪市は、97.3の落ち込みにとどまります。特に、都心回帰傾向による他エリアからの流入が顕著な福島区(114.7)・天王寺区(114.2)・浪速区(111.9)・西区(120.7)・北区(117.8)・中央区(121.1)では、1割以上の増加が予測されています。一方、港区(84.6)・大正区(82.7)・生野区(87.0)・東住吉区(86.7)・西成区(71.9)・住之江区(86.8)・平野区(88.5)は9割を切るという厳しい状況です。特に西成区は、都道府県別最下位の秋田県を下回っています。
こうした人口推移は、大阪市内における住宅地の地価の二極化にますます拍車を掛けるでしょう。
世帯数の動向に注目しよう
人口減がすでに始まっている一方で、2023年までは世帯数が増加し続けるとされています。これには世帯構造の変化が影響しており、今まで標準世帯と呼ばれてきた夫婦と子ども2人の世帯が減少し、夫婦だけ、または単独の世帯が急速に増加していくのが主な理由です。特に単独世帯は、2015年の1,842万世帯から2030年には2,025万世帯と、約1割も増加すると予測されています。単独世帯は標準世帯に比べて持ち家志向が弱く、賃貸需要が高いとされています。
少子高齢化と人口減少が進むといっても、全国均一というわけではありません。また世帯構成も刻々と変化していきます。不動産投資でビジネスチャンスを見いだすためにも、こうした動向はたえずウォッチしておきましょう。
人気の記事ランキング
キーワードから記事を探す
注目の不動産投資セミナー
大阪・京都・神戸

大阪・京都・神戸の物件を希望の日程で見学できる物件見学会を開催中!
- 日程
- 適時開催
- 会場
- 見学対象の区分中古マンション
名古屋

名古屋の物件を希望の日程で見学できる物件見学会を開催中!
- 日程
- 適時開催
- 会場
- 見学対象の区分中古マンション