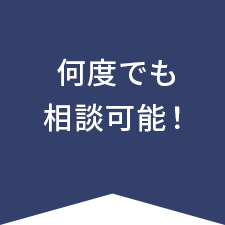数年前まであまり知られていなかったふるさと納税ですが、2016年度から急激にふるさと納税をする件数が増加しました。総務省の統計によれば、住民税における2018年度の寄附金控除適用者数は約296万人、控除額は約2,448億円になり、前年に比べていずれも1.3倍以上となっています。
しかし、地方自治体同士の競争激化が問題として表面化し、中には財政基盤が危うくなる自治体も出てきています。その影響から、2019年度以降、ふるさと納税はこれまでほどのメリットが享受できなくなります。
ふるさと納税とは何か
ふるさと納税とは、もともと地方から都心に移住した人が生まれ育った地域などに感謝の意をこめた寄附を行ってもらうことを促す制度として創設されました。高度成長期以来、地方で育った人がいったん就職や就学などで都市部に出ると、そのまま都市部で生活し、故郷に戻らないスタイルが増えました。結果、地方自治体は急激な少子高齢化と過疎化が進み、地方行政に必要な税源も確保できない状況に悩まされています。この状況を解決すべく始まったのがふるさと納税だったのです。
当初、ふるさと納税には3つの意義がありました。寄附をすることで寄附したお金の使途や税金に関心を持ってもらうこと、生まれ故郷を含めた地方への感謝や応援になること、そして地方団体と住民自ら地方自治のあり方を考えるきっかけにしてもらうこと、です。そして、返礼品もあくまでも地域のよさを伝えるノベルティだったのです。
また、名称はふるさと納税となっていますが、実際は「地方自治体への寄附」に当たります。そのため、ふるさと納税を行うと所得税の寄附金控除や住民税の寄附金税額控除を受けることができます。ただ、無制限に寄附金控除や寄附金税額控除を受けることができるわけではなく、所得税でも住民税でも上限が設けられています。自分自身の寄附金の上限額を事前に計算し、その枠内で寄附すれば、寄附した金額から2,000円を差し引いた金額だけ税金が安くなる仕組みです。
ふるさと納税による問題
かつてほとんど知られることのなかったふるさと納税ですが、節税のメリットや豪華な返礼品が知られるにつれ、ふるさと納税を行う納税者が急増しました。ふるさと納税の意義ではなく「2,000円で豪華な返礼品がもらえる」という認識の方が広まったのです。
同時に、自治体同士の返礼品競争が激化、中には商品券や旅行券、高額電化製品を返礼品として送る自治体も登場しました。これにより、かつて都市部と地方の間の問題であった格差が、今や地方自治体同士のものとなりました。
さらに、横浜市や東京23区など人口が多い都市部から税が流出、今後の行政運営が危うくなる懸念が表面化しました。地方自治体では職員たちがふるさと納税の寄附金処理や返礼品の出荷作業に追われ、本来の行政事務が行えないところも出てきました。
この事態を重く見た総務省はこれまで何度か自治体に返礼品を自粛するよう呼びかけを行いましたが、ほとんど効果がありませんでした。そこで、2019年度税制改正において、ふるさと納税の特例控除の基準が明確に設けられることになったのです。
2019年6月以降、返礼品はこうなる
2019年度の税制改正により、2019年6月以降のふるさと納税では、地方自治体の返礼品に次の2つの基準が設けられる予定です。
- 返礼品は地場産品に限定すること
- 返礼品の調達費は寄付額の30%以下にすること
この2つの基準を守らない返礼品を行った自治体は、指定自治体から外される予定です。つまり、納税者が豪華な返礼品狙いでふるさと納税を行った場合には、寄附金に係る住民税の特例控除が適用されなくなることが想定されています。
ただ、指定自治体から外れた自治体に行った寄附であっても、所得税や住民税の基本控除の適用はあると思われます。赤十字や認定NPOなどへの寄附と同じような扱いになるだけです。
今回の改正により、「ふるさと納税に旨みがなくなる」「地方自治体の財源基盤を強くするためのものなのに、寄附が減ってまた地方財政が危うくなる」といった声が聞こえてきます。しかし、ふるさと納税のそもそもの意義はお金だけではありませんでした。なぜうまくいかなかったのか、どこを変えるべきなのか。今回の税制改正は、一度冷静になって原因を検証するよい機会なのかもしれません。
人気の記事ランキング
キーワードから記事を探す
注目の不動産投資セミナー
大阪・京都・神戸

大阪・京都・神戸の物件を希望の日程で見学できる物件見学会を開催中!
- 日程
- 適時開催
- 会場
- 見学対象の区分中古マンション
名古屋

名古屋の物件を希望の日程で見学できる物件見学会を開催中!
- 日程
- 適時開催
- 会場
- 見学対象の区分中古マンション